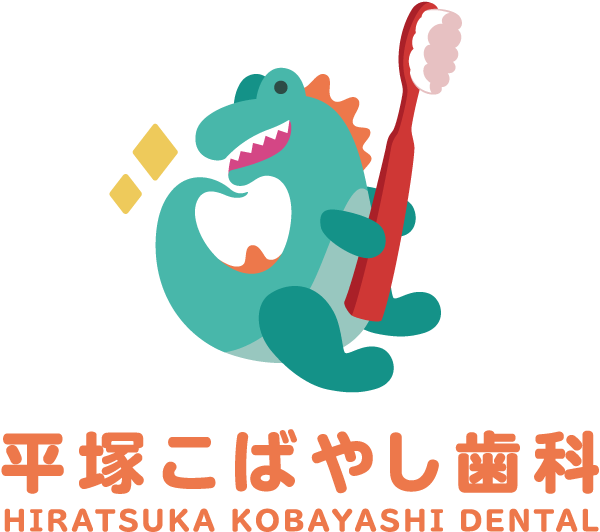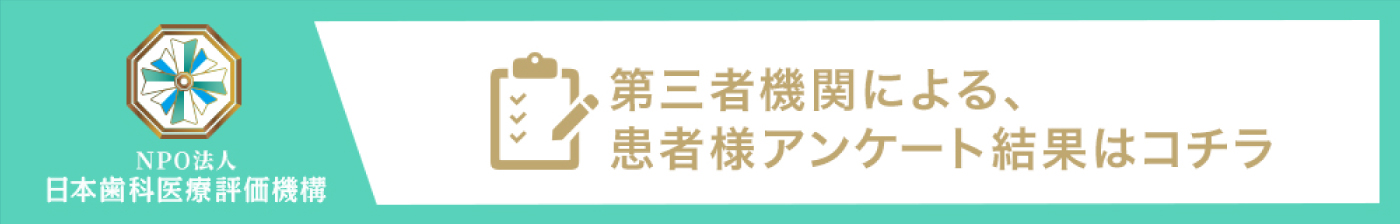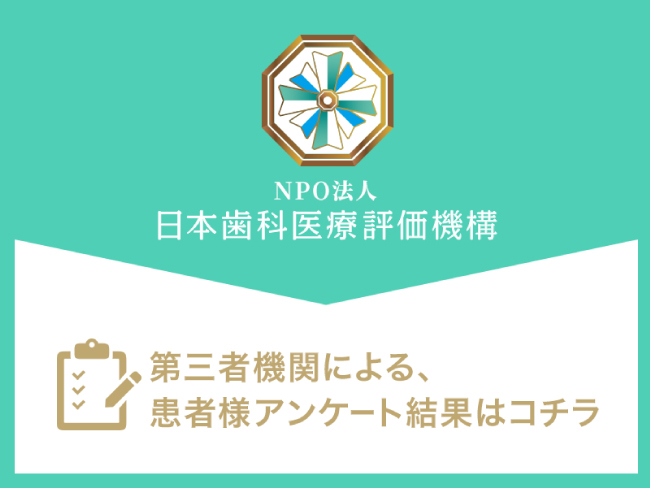歯ぎしりの原因と解決策のマウスピースとは
近年のストレス社会において、歯ぎしりをする方が増えていると言われています。 周りから言われないからしていない、自覚症状がないのでしていないという方も多いと思います。 しかし実際はほとんどの方が歯ぎしりをしていると言われます。 今回はその歯ぎしりがもたらす悪い点や歯ぎしりの対策を説明していきます。 気づいた時には手遅れになる前にしっかりと予防をしていくことが大切になっていきます。 歯ぎしりの種類について 歯ぎしりと言うとギリギリやカチカチと音がするイメージがあると思いますが、それが全てではありません。 まずは歯ぎしりの種類について説明していきます。 1.グライディング(ギリギリ歯ぎしり) これは一番イメージされている、上下の歯を横にすり合わせて動かす歯ぎしりです。 寝ている間にギリギリと音がするといわれるのが一番多いタイプです。 これの特徴としては一番歯がすり減って削れていくことです。 上の歯の前から3番目の犬歯が削れていき平らになることもあります。 またその犬歯が大きく削れていくと、奥歯にも影響が出てきて最終的には噛み合わせ全体に影響を及ぼします。 2.タッピング これはご飯を食べるように上下に歯を動かし、カチカチと音が鳴る場合もあります。 横に動かす歯ぎしりより音が小さかったり、歯が削れたりしないので最も気づかれにくい歯ぎしりかもしれません。 それでも元々の咬み合わせが悪かったりすると、歯に影響を及ぼしたりします。 3.クレンチング(食いしばり) これは歯を噛んだ状態から強く噛みこむいわゆる食いしばりです。 この場合は音がほとんどないので、周りから気づかれることはほとんどありません。 症状としては朝起きると顎や歯が痛い、筋肉が痛い、肩こりや頭痛を引き起こすこともあります。 また、寝ていない起きている活動中でも無意識でやっていることもあります。 運転中や料理中など何かに集中していて、無意識で噛みこむ癖がある人もいます。 噛む力が強い日人は歯が欠けたり、最悪の場合は歯が折れたり、根っこが割れたりして抜歯をしなくてはいけなくなることもあります。 朝起きて咬筋といって耳の前の筋肉が固くなっていたり、痛い人は要注意です。 歯ぎしりの原因とは 歯ぎしりは様々な要因が重なって起きていると言われています。 しかし正確なメカニズムはわかっていません。 それでもほとんどの人は程度の差はあるものの、何かしらの歯ぎしりをしていると言われます。 ではどのような要因によってする機会が増えるのかを説明していきます。 1.ストレス これは一番よく言われるものですがストレスが多くかかる状況だと歯ぎしりが増えるとされます。 またその強度も強くなり、歯や顎や筋肉にかかる負担も格段に増えます。 普段は症状がない人でもストレスが多い時にだけ自覚する人もいるかと思います。 できるだけストレスをためすぎない、またその状況を改善するように気を付けることが大切です。 2.体調不良や疲れ さきほどのストレスと重なるところがあるのですが、身体的疲労や風邪などの体調不良によっても歯ぎしりが増えるとされます。 一時的なものが多いので体調が回復すると歯ぎしりも改善することが多いです。 3.その他 他にも様々な要因が絡むのですべて特定することは難しいです。 また子どもでも強く歯ぎしりをする子がいらっしゃいます。 この場合は原因を探すのがより難しいかと思います。元々の癖でやっている場合もあるかと思います。 歯ぎしりがもたらす影響とは ではなぜ歯ぎしりをするのがいけないのでしょうか。 歯ぎしりがもたらす影響がどのようなものがあるか説明していきます。 1.歯が削れる 横に動かす歯ぎしりをすることによって犬歯と呼ばれる前から3番目の歯が削れていきます。 そうなると奥歯の噛み合わせが強く当たるようになったりすることにより、噛み合わせが悪くなったり、歯に負担が多くかかるようになります。 歯が削れたり負担が多くかかる時間が続くと、歯が欠けたり割れたり、最悪の場合歯の根っこが割れたりしてしまうこともあります。 2.歯がしみるようになる 歯が削れてくると固いエナメル質と呼ばれる層がなくなってきます。 そうなるとその下の象牙質と呼ばれる層が露出すると神経までの距離が近くなり冷たいものや温かいものの刺激が受けやすくなりしみやすくなります。 また歯と歯ぐきの境目のあたりが歯ぎしりによって削れたり欠けてきたりします。 そうなると先ほどと同じように象牙質が露出することにより、しみる症状が出やすくなります。 3.顎関節症になる 食いしばりなどの歯ぎしりをすると、耳の前あたりにある顎の関節に負担が強くかかる時があります。 この状態が続くと顎が痛くなる、口が開きにくくなる、筋肉が痛くなるなどの症状がでます。 4.歯の骨が減る 歯ぎしりが続き歯にダメージがかかっていると、歯を支えている骨にもダメージがかかっていきます。 徐々に骨が減ってくると歯がグラグラ揺れてきたり、噛むと歯が痛くなったりしてきます。 最悪のケースは骨が抜け落ちてしまうこともあります。 5.頭痛や肩こりを引き起こす 歯ぎしりや食いしばりが強い人は頭痛や肩こりになる場合もあります。 その他さまざまな症状の原因になることもあります。 歯ぎしりの治療法について 1.噛み合わせ調整 歯が痛いなどの症状がある場合は噛み合わせ調整をすることで改善できます。 ただ改善してもまた強く当たることもあり、何度も調整しないといけないこともあります。 2.マウスピース 保険適応内でマウスピースを作成することができます。夜に寝るときに基本的には上の歯につけて使用します。 種類は固いマウスピースと柔らかいマウスピースがあります。歯ぎしりの種類や症状によってどちらを使うかは変わってきます。 歯ぎしりの治療や予防にはマウスピースが一番お勧めです。 まとめ 歯ぎしりは強い弱いの差はあるものの、ほとんどの方がしていると言われています。 歯が痛い顎が痛い、歯がグラグラするなどの症状のある方は早めに対策をする必要があります。 また、症状がなくても一度チェックをし、予防していくことが大切になってきます。
2025.03.25